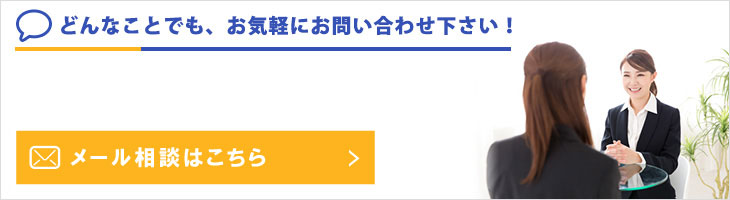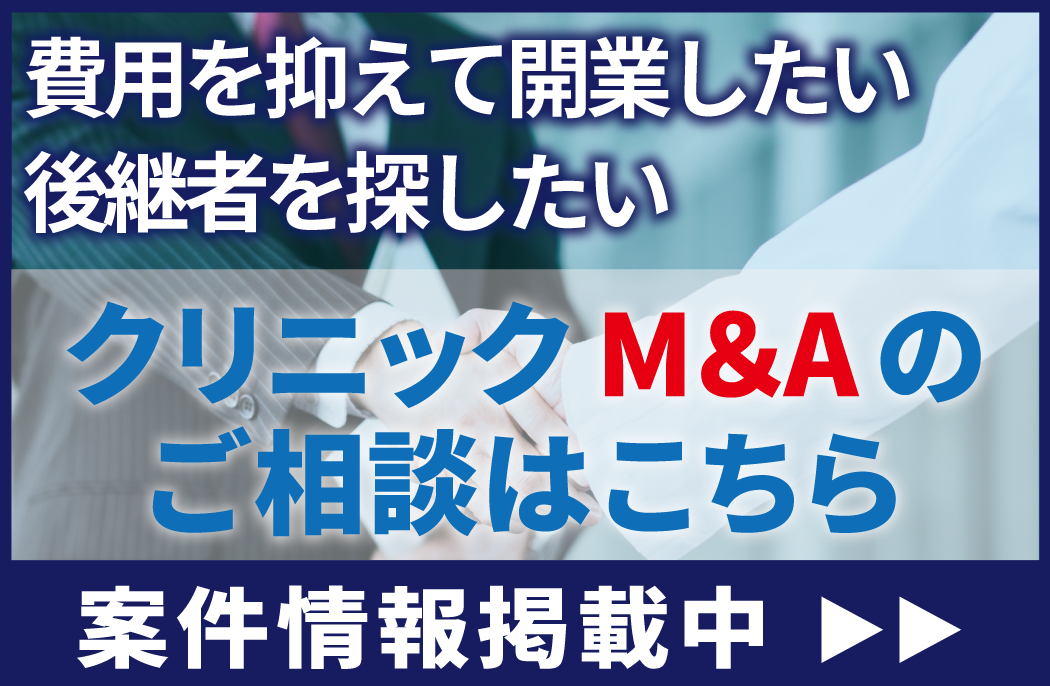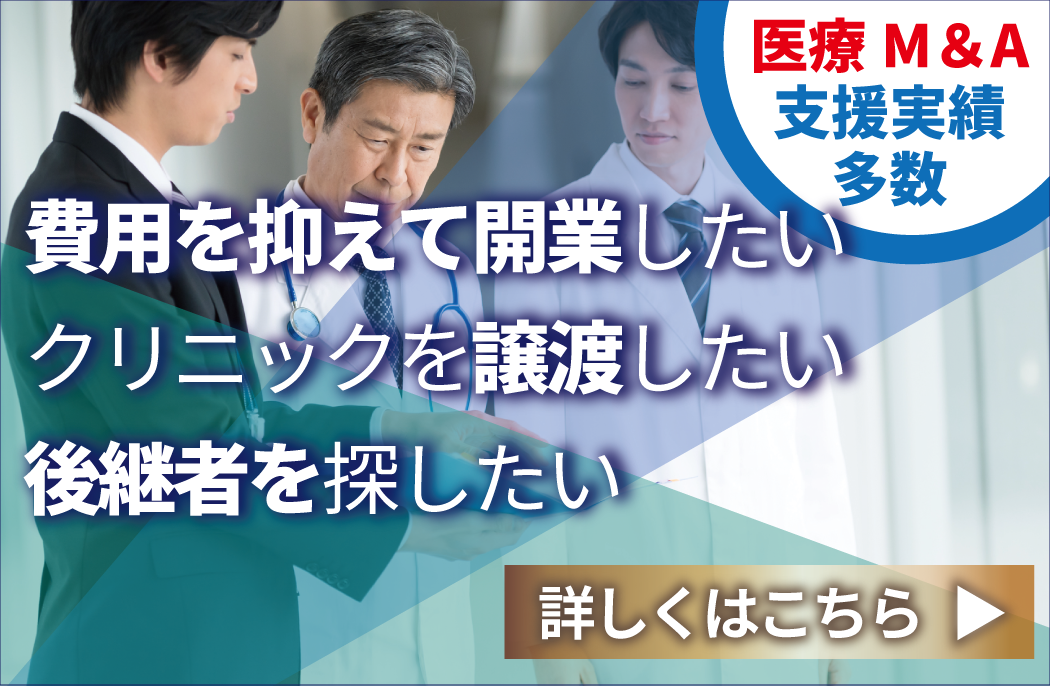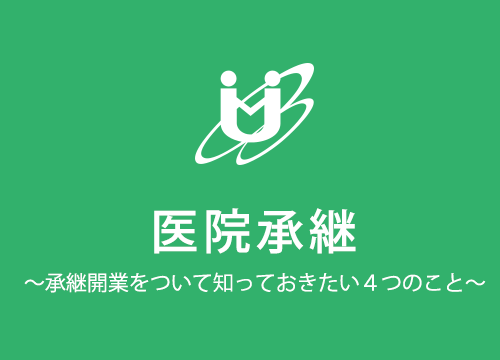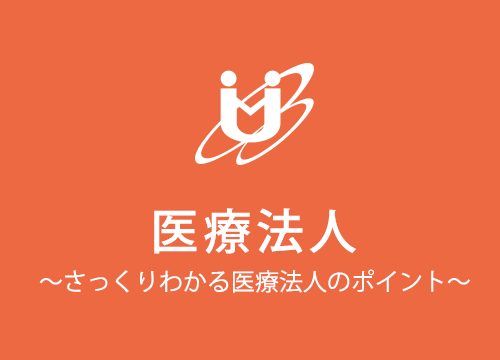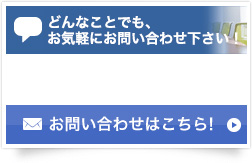【夫婦間の贈与】贈与税の配偶者控除とは?

Contents
1.贈与税の配偶者控除とは?
この制度は、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用の不動産やその購入資金の贈与を受けた場合は、2,000万円までは贈与税がかからないというものです。なお、この2,000万円の中には、贈与税の基礎控除は含まれません。ちなみに、この控除は同一の配偶者からは、1回しか適用を受けることができません。
これにより、贈与者の財産を生前に減らすことができるので、相続税対策とすることができます。趣旨としては、夫婦の財産の形成は夫婦の協力によって得られる。夫婦間における財産の贈与については、贈与という観念が薄い。夫婦間の財産の贈与は、生存配偶者の老後の生活保障を意図しているためです。一見すると非常に有利な制度に見えますが、利用にあたってはいくつかのデメリットや注意点がありますのでご説明していきます。
2.デメリットと注意点
注意点①非課税になるのは「贈与税」だけ
この特例で非課税になるのは「贈与税」だけです。不動産の名義変更には、以下の税金や費用がかかり、これらは相続で取得する場合よりも高額になります。
不動産取得税
相続の場合はかかりませんが、贈与の場合は固定資産税評価額の3%などが課税されます。
登録免許税
不動産の名義変更(登記)の際に必要です。贈与の場合は固定資産税評価額の2%ですが、相続の場合は0.4%です。
注意点②相続税の特例が使えなくなる可能性
相続税の特例が使えなくなる可能性があります。相続税には、自宅の土地の評価額を最大で敷地面積330㎡まで、80%減額できる「小規模宅地等の特例」というものがあります。生前に自宅を贈与してしまうとこの特例が受けることができません。
注意点③贈与された配偶者が先に亡くなるという可能性
贈与された配偶者が先に亡くなるという可能性もあります。その場合、せっかく贈与した財産が贈与者に戻ってくるかもしれません。手間と費用をかけた意味が無くなってしまいます。
注意点④その他
この特例を利用するためには、たとえ、贈与税が0円であっても、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。申告を忘れると特例は適用されず、ただの暦年贈与となり高額な贈与税が課せられます。
3.最後に
この制度を検討した方が良いケースとしては、贈与者の相続財産が非常に多く、相続税の負担がかなり重くなることが予想される場合や居住用財産がなく、これから購入をされる際に、その資金の一部又は全部を配偶者に贈与をする場合が挙げられるかと思います。安易に「非課税だから」という理由だけで、この制度を利用すると、かえって損をしてしまう可能性がありますので、ご検討される場合には、ご自身の財産の状況を把握の上、税理士法人アップパートナーズの担当者にご相談されることをお勧めいたします。
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介