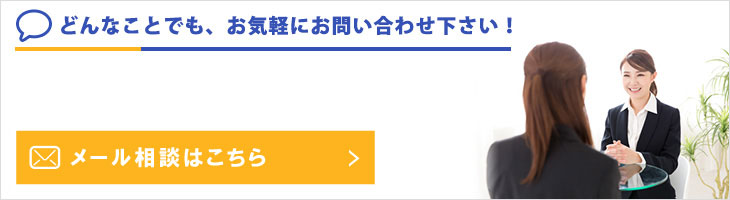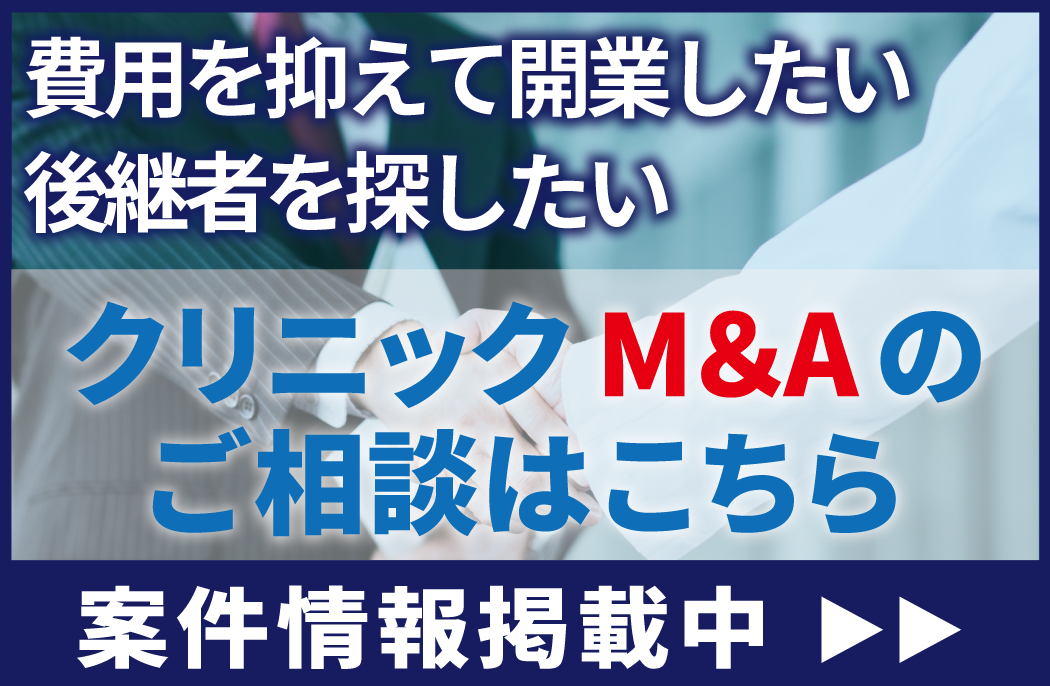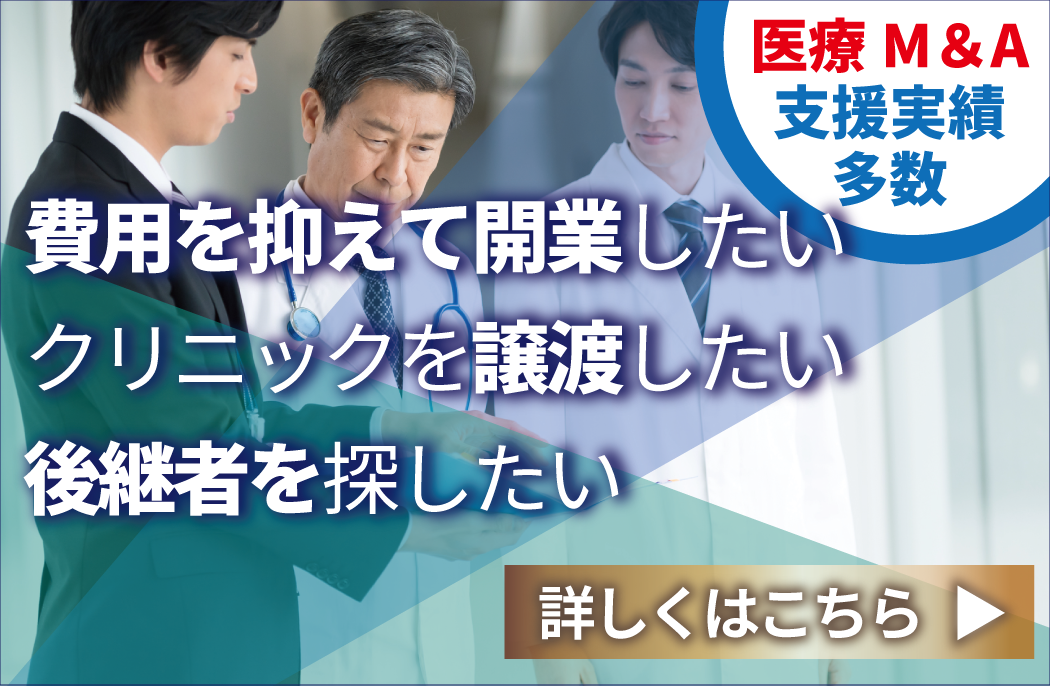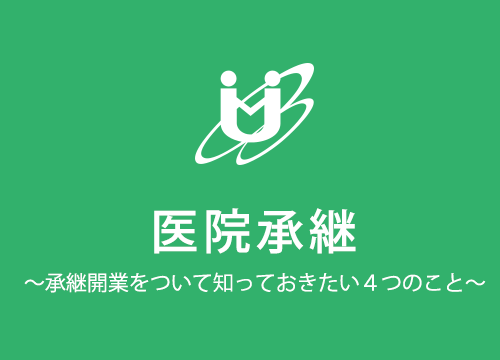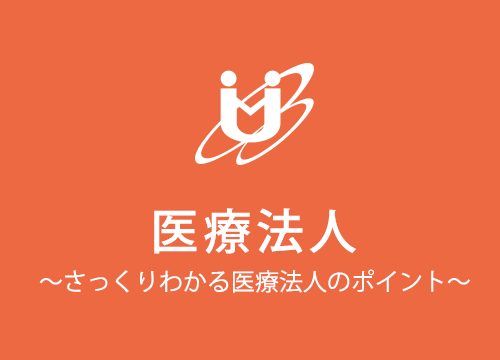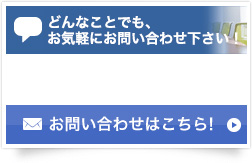確定拠出年金の老齢一時金に関する改正

1.はじめに
確定拠出年金とは個人型(iDeCo)のものと企業型(企業型DC)と2種類あります。
2025年の税制改正により確定拠出年金を一時金で受け取った場合の退職所得控除の調整規定の対象となるケースが変更となったためご紹介いたします。
2.確定拠出年金とは
確定拠出年金とはどちらも老後の資金形成を目的とした私的年金制度です。掛金を拠出し、運用商品で運用したものが年金額となります。個人型と企業型についてどのようなものか簡単に紹介いたします。
まず個人型確定拠出年金についてですが、掛金が全額所得控除となるため、所得税・住民税が軽減されます。また運用益が非課税となるのも魅力です。ただしデメリットとして目的が老後資金ということもあり原則60歳まで資金を引き出せないということや、運用次第では元本割れのリスクがあります。
一方企業型拠出年金は、基本的には企業が掛金を拠出するため、従業員は給与課税されません。こちらも運用益が非課税となっているのも魅力です。ただし原則60歳まで資金を引き出せないということや、運用次第では元本割れのリスクがあるのは個人型と同じですが、転職・退職時に手続きが必要だったり、運用商品が限定されていたりと個人型より制限されるところもあります。
3.今回の改定について
前述のように確定拠出年金には大きなメリットがあり、どちらも受取時に関しては年金として受け取るか一時金として受け取るか選べます。今回一時金として受け取る場合について改定がありました。一時金で受け取る場合は退職所得となるため退職所得控除を受けることができます。
退職所得控除の計算式は下記のとおりです。
・勤続年数20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数20年超の場合:800万円 + 70万円×(勤続年数 – 20年)
上記計算式で退職所得控除の金額つまり、無税となる金額を求めます。
※企業型確定拠出年金の場合は掛金を支払った年数
いままでは「退職所得等の支払を受ける年の前年以前4年以内に他の退職手当等の支払いを受けている場合」と、「確定拠出年金に係る一時金の支払いを受ける年の前年以前19年以内に他の退職手当等を受けている場合」は先程の計算式で算出した金額に退職所得控除の調整が行われていました。
退職所得控除の調整とは、短期間に複数回退職金や確定拠出年金の一時金を受け取る場合に、退職所得控除が重複して適用されることを防ぐための仕組みです。
退職所得控除が適用される例として、複数の会社に在籍し、A社を退職して退職金を受け取り、その2年後B社も退職し、退職金を受け取った場合です。
こちらは退職所得等の支払を受ける年の前年以前4年以内に他の退職手当等の支払いを受けている為、A社での勤続期間とB社での勤続期間に重複があるため、その重複期間については退職所得控除の計算から除外されることがあります。
※最初の退職金の金額や状況によって変わりますのでそちらは税理士などにお尋ね下さい。
上記のように退職所得控除に調整が必要なケースが2つあったが、今回の改定で新たに1つ追加されました。
今回の追加は「退職所得等の支払いを受ける年の前年以前9年以内に確定拠出年金の支払いを受けている場合」です。
今までは確定拠出年金の一時金を受け取り、そこから5年経過後に退職手当等を受け取れば両方とも退職所得控除に調整が必要とされませんでしたが、今回の改定で10年近く間をあけないと調整が必要となる改定をされております。
4.終わりに
今回の改定により、今まで以上に確定拠出年金の一時金受け取りと退職手当等の受け取りタイミングについて検討が必要となっております。医療法人では加入できませんが、小規模企業共済に加入されている場合は、小規模企業共済の解約一時金についても退職手当等になるためより検討が必要となります。
受け取りの順番によって老後の資金が変動しますので一度担当の税理士へ相談されることをおすすめいたします。
▼関連記事
退職金制度導入の際の「確定拠出年金制度」の活用
https://www.upp-medical.com/column/clinic-management/9101/
- 病院・クリニックの方へ
- 歯科の方へ
- 新規開業をお考えの方へ
- 医療法人設立をお考えへ
- 事業承継・相続・売却をお考えの方へ
グループのサービスご紹介